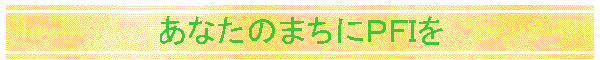
�@�@�@�@�@�@�@
|
|
|
��P���@�o�e�h�Ƃ͉��� ��P�́@���A�n�������̂ɋ��߂��邱�� �P�@�s�������v�̂��߂̐V�����l���� �@�ߔN�A�n�������̈�������w�i�ɁA�S���̒n�������̂ł́u�������ƕ]���E�����]���v��u�o�����X�V�[�g�v�A�u�o�e�h(Private Finance Initiative�j�v�ȂǁA�s���^�c�̐V�������P��@����������A�����������B �@���������V������@�̈�ł���o�e�h�Ƃ́A�u�����{�ݓ��̐v�A���݁A�ێ��Ǘ��y�щ^�c�ɁA���Ԃ̎�����m�E�n�E�������p���āA�����T�[�r�X�̒Ԏ哱�ōs����@�v�̂��Ƃł���B�o�e�h�ł͌_����Ԃ������ꍇ�ɂ́A20�`30�N�ɂ��y�ԁB�����̎�茈�߂��A20�N�A30�N�ƈ����������Ƃ��l����A�����ɍŏ��̌_����e������͑z���ł��悤�B �@�܂�A�o�e�h�ł́A���̖{���𐳂����������A�����ɂo�e�h�̓��������������_������Ԃ��Ƃ��ł��邩�A���|�C���g�ɂȂ�B�o�e�h�̓������Ȃ����߂��Ă���̂��A�o�e�h�̍���ɂ���l�����͉������A�������n�������̐E���ɗ�������Ă��Ȃ���A�K�Ȍ_���ׂ��A�o�e�h���L���ɋ@�\���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����낤�B (�P) ���܂��܂ȏZ���j�[�Y�ƍ��� �@��ʂɎЉ���n������ƁA�Z���j�[�Y�����l���E���x������B �@�ߔN�A���̈�ʉ�v�Ώo�z�́A�}���ɐL�тĂ���B�܂��A���c����(���Ƀo�u������ȍ~�A�i�C�̉Ɍ������o�ϑ�̉e��������)�E���オ��ƂȂ��Ă���B�i�}�\�T�|�P�j
�@ �@��ʌ��̏����l�ł���B�������s���̉e���ɂ��A���Ŏ����͕����R�N�x���s�[�N�ɁA���̌����𑱂��Ă���A11�N�x���Z�z�́A2�N�A���őO�N�x��������Ă���B���̈���ŁA���̌o�ϑ�ɑΉ��������Ƃ����{���邽�߂ɔ��s���ꂽ���̗ݐώc���������̈�r�����Ă���A12�N�x���c��(������)�͂R�N�x����3.3�{�ƂȂ�B�i�}�\�T�|�Q�j�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�\�T�\�Q�@���c���̐���
�@��ʌ����̎s�����ɂ����Ă��A�n���̎c���͈�т��ĐL�тĂ���A�U�N�x����́A�n���c�����W�������K�͂������ԂɂȂ��Ă���B10�N�x�́A�W�������K�͂ɑ��ċN�c���͖�1.23�{�ł���B�i�}�\�T�\�R) �@�@�@�@�@�@�}�\�T�\�R�@�����s�����n�����ݍ��A�W�������K�͂̐���
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�i�C�̖{�i���}���ɂ͊��҂ł��Ȃ����ŁA�ݐς��Ă��鍑�A�n���́A�m���ɏ��҂��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������̒��ŁA����̗v������s���ۑ�ɓK�ɑΉ����邽�߂ɁA�������x�̉��P�͋i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă���B �@�n�������̂ł��A��������ւ̉ߓx�ȕ��S������邽�߁A����܂Łu�Ώo�J�b�g�E�l���팸�E�g�D�̃X�������v�Ȃǂ̎��ȉ��v���Ȃ���Ă����B��ʌ��ł��A11�N10���Ɂw�s�������v�v�����x�����肵�A�@���s���̃X�������A�A���s���̎d�g�݂̉��v�A�B�����̋���������Ղ̊m���Ɍ��������{�I���v�����s���Ă���Ƃ���ł���A�����e�s�����ł����l�̓���������B �@���̈���ŁA�����T�[�r�X�̎�ł���Z���́A����ł͕K�������������Ă��Ȃ��B(��)�o�ύL��Z���^�[���A11�N�R���ɍs�����w�n���s���Ɋւ���A���P�[�g�x�ɂ��ƁA�n�������̂̌����T�[�r�X�ɂ��āA��S���̂R�̏Z�������炩�̕s��������Ă���B�i�}�\�T�|�S�j�܂��A��s���𒆐S�Ƃ���T�����[�}����85�����A�u�ŕ��S�Ɍ������������T�[�r�X���Ă��Ȃ��v�Ɗ����Ă���Ƃ������������@������A�n�������̂́A���̂悤�ȕs�����Ɏ~�߂�K�v�����낤�B �@���l���E���x�������Z���j�[�Y���ׂĂɉ�����̂͌����I�ɖ������Ƃ��Ă��A����n�������̂̉��v�́A����ꂽ�\�Z�̒��ŁA�����Ɍ����ǂ����̍����T�[�r�X���Z���ɒł��邩�ɂ������Ă���B 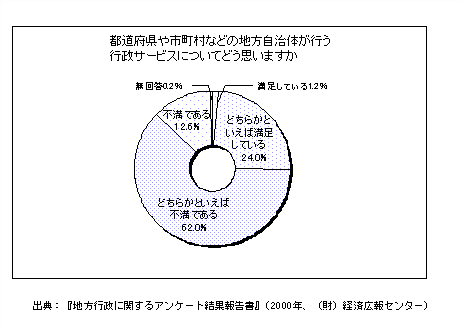
�@
�@�@�@�@ �n�������̂̑䏊����
�����s�����̍������A��ʉƒ�̉ƌv��ɒu�������čl���Ă݂܂��傤�B
(�Q) �m�o�l(New Public Management)���_ �@���̂悤�ȁu�Z���̎��_�ɗ��������v�v���čs�����̂�1980�N��̉p���A1990�N��̕č��ł������B���ɁA80�N��܂ł̉p���́A�䂪���̌���Ɣ��ɍ������Ă���B�����̉p���́A������u�p���a�v���������A�o�ς������ɂ킽�������A������[�������钆�A�����T�[�r�X�̎����������ቺ���Ă����B���̂悤�ȏ̒��ŁA�T�b�`���[�����́A�����T�[�r�X�ɂ��s�ꌴ�����ɗ͓������A���̂��Ƃɂ���Ď��ƌ����̗�����Nj����邱�Ƃ��l�����̂ł���B�č��ł��A��Ƃ̌o�c���v�̎�@���A�܂��͐�i�I�Ȓn�������̂ɁA�����čX�ɒ������{�ւƓ`�d���A���т������Ă����B �@�����p���E�č��̉��v�ɋ��ʂ���l�����́A���Ԋ�Ƃ̌o�c��@�̒�����s���ɉ��p�\�Ȃ��̂�I�яo���A�������Ă������Ƃ�����̂ł���B���̊�{�������܂Ƃ߂�ƁA�@�Ɛс^���ʂɂ�铝���A�A�s�ꃁ�J�j�Y���̊��p�A�B�ڋq��`�ւ̓]���A�C�q�G�����L�[�ȑf���̂S�ƂȂ�B �@�@�Ɛс^���ʂɂ�铝���Ƃ́A�s���^�c�̕]���ɂ�����A�u�ǂ��s�������v(�@�I�葱�̑Ó����Ȃǁj�ł͂Ȃ��A�u�s�������ʁA�����ǂ��ς�������v�Ƃ����Ɛс^����(�A�E�g�J���j���d�����邱�Ƃł���B�����āA���肵���Ɛс^���ʂɊ�Â��āA�\�Z��l���Ƃ�������������(�C���v�b�g�j�A�T�[�r�X�̓��e(�A�E�g�v�b�g�j���������A���P��i�߂Ă����B �@�������A����܂ł̓`���I�ȍs���V�X�e���́A�Ɛё��蓙�̌o���ɖR�����A�������J�j�Y���������Ȃ����߁A�u�Ɛс^���ʂɂ�铝���v�����҂ǂ���ɋ@�\���Ȃ������ꂪ����B �@�����ŁA�A�s�ꃁ�J�j�Y�������p����B���������̓����ɂ��A�������⎿�̌����ڎw���A�X�Ɂu�_��v�̊T�O����������Ɏ�����āA�Ɛс^���ʂɂ�铝���̎����������߂邱�ƂƂȂ�B�u�_��v�ɂ��s���^�c�V�X�e���Ƃ́A����(���E����)����Ǝ��{(�T�[�r�X��)��������A�u���炩���ߌ��߂�ꂽ�ƐіڕW��B�����邱�Ɓv�������ɁA�\�Z��l�����ɂ�������{����̍ٗʌ����g�傷�邱�Ƃł���B���̌��ʁA���{����ɂ͑n�ӍH�v�̗]�n�����������A����܂ňȏ�Ɍ���(�Ɛт�ʁj���d������邱�ƂɂȂ�B�_��^���f���ɂ́A���Ԉϑ���G�[�W�F���V�[�A�o�e�h�ȂǗl�X�ȃp�^�[��������A����T�[�r�X�̐��i�ɉ����čł��ӂ��킵���p�^�[����I������B �@�B�ڋq��`�ւ̓]���Ƃ́A�����T�[�r�X�̗��p�҂��邢�͔[�Ŏ҂��u���q�l�v�ƌ����āA���̖����x���ő剻���邱�Ƃ��s���̎g���Ƃ�����̂ł��邪�A���ɁA�Ɛс^�]���̑���̏�ʂŁA�ڋq(�Z���j���]�ސ��ʂ���Ƃ��ׂ��_���d�v�ł���B �@�C�q�G�����L�[�ȑf���Ƃ́A�Ɛс^�]���̑��肪���₷���悤�ɁA�g�D���Ɩ��P�ʂɍו����E�ȑf�����邱�Ƃł���B �@�ȏ�̃R���Z�v�g�̎����ɂ��A���Ԋ�Ɠ��ōs���Ă���o�c��@�̃����b�g���s���^�c�ɂ��������ꂽ���ʁA�p�Ă̍s�������v�͑傫�Ȑ��ʂ������邱�ƂƂȂ����B����������@���A�u�㔭�҂̃����b�g�v�������Ɋ������Ȃ���A�䂪���̕��y�ɍ����悤�Ɋ��p���Ă����Ă͂ǂ����낤���B�Z�����u�łɌ��������T�[�r�X�v���Ă��邩�ǂ����A�s�������߂Ė₢�����A���P���Ă����A���̎��_�����������̍s�������v�̐��i�ɕs���ł���B �@���Ԋ�Ƃ̌o�c��@���ɗ͍s���̌o�c�ɂ����f�����Ă������Ƃ����l�����́A�u�j���[�E�p�u���b�N�E�}�l�W�����g���_(�m�o�l���_)�v�ƌĂ�Ă���B�䂪���ł́A�O�d�����n�߂Ƃ��A��i�I�Ȓn�������̂̍s�������v�Ɏ�������Ă���l�����ł���B
�@�@�@�@�@ �C�O�ł͂���ȂɁw���q�l���x �w���q�l����`�x�Ƃ������t���ƁA�܂��A���Ԋ�Ƃ��v�������ׂ邩������܂���B�������Ȃ���A����͍s���̐��E�ł����Ă͂܂�܂��B �@�Ⴆ�A�A�����J�̒n�������̂́A�܂��Z���j�[�Y�̃q�A�����O��A���P�[�g���������Ƃ��͂��߁A�������玖�ƕ]���◧�Ă��s���Ă��܂��B�|�[�g�����h�s�́A�s���T�[�r�X�ւ̏Z���̖����x���A�N�Ɉ�x�̃A���P�[�g�Œ������Ă��܂��B�܂��A�w�d�b�s���P�P�O�ԁx������A�������ł��t����d�g�݂����Ă��܂��B�J���t�H���j�A�̃T�j�[�x�[���s�ɂ����ẮA�e���ǂ��K���������Z���j�[�Y�̒������s���Ă��܂��B�����ł́w�ڋq�u���x�������Ɏ�������Ă���̂ł��B
�Q�@�ς��s���̖��� �@�u�ڋq�ł���Z���̖����x���厖�v�Ƃ����̂́A�����͂��₷���A�������s����ƂȂ�Ƃ����e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�s���͏Z���̂��߂Ǝv���Ă��Ă��A���ꂪ�{���ɏZ���̂��߂ɂȂ��Ă��邩�A�s�����������ł͂킩��Ȃ�����ł���B�Z���j�[�Y�����l���E���x����������ł͂Ȃ�����̂��Ƃł���B �@�����ŁA�����T�[�r�X�����҂Ƃ��̃T�[�r�X�̕]��������҂�ʂɂ��悤�Ƃ������z�����܂�Ă���B����ɂ���ĕ]���̋q�ϐ����m�ۂł��邩��ł���B����܂ł̍s���́A�������傪��旧��(Plan�j���A���s���傪��������{(Do�j���A�����ċc�������傪���̎��т�]��(See�j���A���̕]�����ʂ��t�B�[�h�o�b�N���Ď��̐������Ăɖ𗧂Ă�Ƃ����X�^���X���Ƃ��Ă����B �@�o�e�h�ł́A�]���̋q�ϐ����m�ۂ��A���{�����T�[�r�X�̌������Ǝ�����荂�߂邽�߁A����܂Ŏ����(Do�j���Ă��������T�[�r�X���A���Ԏ��Ǝ҂ɒ�(Do�j������B�s���́A�]��(See�j�A��旧��(Plan�j�Ȃǂ̎����ɓ�������B�܂�A�s���́A�u�ڋq�ł���Z���v�̂��߂ɗǎ��Ȍ����T�[�r�X������Ă��邩���������`�F�b�N����ƂƂ��ɁA�u�ڋq�ł���Z���v���]��ł��邱�Ƃ𐳂����c�����A�T�[�r�X�̒�(���Ԏ��Ǝҁj�ɑ��A�Z���j�[�Y���ق�������ւƕω�����̂ł���B �R�@�o�e�h�̖{�� �@�����T�[�r�X�Ԏ��Ǝ҂ɒ�����(�s�ꃁ�J�j�Y���̊��p�j�Ƃ����Ă��A��̓I�ɂ͂ǂ̂悤�ɂ���̂��낤���B �@����ɂ��ẮA�����Ɩ���C����̂ł͂Ȃ��A���D�i�K�A���Ǝ��{�i�K�ŋ������������A���ǂ����̂ݏo������d�g��(�_��)�����B�o�e�h�ł́A���D���ɁA�����̎��Ǝ҂����Ă���̂͂������̂��ƁA�]���ǂ���s�����g�����Ƃ����{������@�ƁA�o�e�h�ōs�����ꍇ�Ƃ��r����B�]�����@�̕����]�܂�����A�o�e�h���̗p���Ȃ����Ƃ�����B���{�i�K�ł́A���Ԏ��Ǝ҂��A����T�[�r�X�������ł��ǂ����̂ɂ��悤�Ƃ��邽�߂̎d�|�������B �@�܂��A�o�e�h�ł́A���Ԏ��Ǝ҂�����̃m�E�n�E���\���ɔ����ł���悤�ɁA���Ԏ��Ǝ҂ɍٗʂ�^���������������Ƃ���B�s���́A�ڋq�ł���Z���̎��_�ɗ����āA�Z�����]�ތ����T�[�r�X���ق��A�T�[�r�X�������������`�F�b�N����̂ł���B �@���̂悤�ɁA�o�e�h�́A��ƌo�c�A�s�ꌴ���Ɋ�Â����s�������v�̋�̓I����̈�ł���A�����T�[�r�X�̌������Ǝ��̌�����ɒNj����A�Z���Ɂu���ǂ������T�[�r�X�v����邽�߂̎�@�ł���B�������Ȃ���A�o�e�h���͕̂]����@�ł͂Ȃ��B�T�[�r�X�҂ƕ]������҂��������A�q�ϓI�ɕ]���ł��邪�ł����ɂ����Ȃ��B�^�Ɍڋq(�Z���j�̂��߂ɂȂ��Ă��邩���f���邽�߂ɂ́A�o�e�h�Ƒ��̕]����@��g�ݍ��킹�āA�o�e�h���Ƃ�i�߂Ă������Ƃ��]�܂����B�܂��A�s�ꃁ�J�j�Y���̊��p�Ƃ́A���������̓������Ӗ����邪�A�u�����v�͒P�Ȃ鉿�i�����ł͂Ȃ��A�T�[�r�X�̓��e���ΏۂƂȂ�B���̂��߁A�Z�����ቿ�i�����T�[�r�X�̎���]�߂A���������͂��̗v�]�ɏ\���ɉ�������̂ł���B �@ �͂��߂ɂƖڎ��@�ɖ߂� �@ �@ |