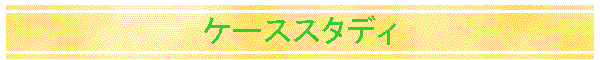
|
|
|
第4部 ケーススタディ 第8章 ケーススタディ 1 ケーススタディの目的 「PFI基本方針」の中に「公的財政負担の見込額の算定に当たっては、財政上の支援に係る支出、民間事業者からの税収その他の収入等が現実に見込まれる場合においてこれらを調整する等適切な調整を行って、将来の費用(費用の変動に係るリスクをできる限り合理的な方法で勘案したものとする。)と見込まれる公的財政負担の総額を算定の上、これを現在価値に換算することにより評価する」という記述があるが、実際に財政負担の比較をすることは容易なことではない。 公的財政負担の総額はライフサイクルコストや定量化されたリスクを積み上げて算定するが、その方法については確立したものがなく、現状ではコンサルタントなどに委託して算定するケースが多い。しかし、PFI事業を検討する際に地方自治体職員がイニシアティブをもって進めるためには、これらの算定方法がどのような仕組みで成り立っているかを、ある程度は認識しておいたほうが良い。そこで、PSCの算定と財政負担軽減の尺度であるVFM算定を試みることとする。VFMの算定に当たっては簡単なキャッシュフロー分析を行う。ファイナンス関連用語についても簡単にふれることとする。 (1) 施設の概要等 事例の算定の参考にした施設は市営で、建設費約10億円、財源は補助金1割、起債7割、一般財源2割で建設した25メートル8コースの大人用プールと幼児用のプールを有する屋内施設で、ケーススタディではほぼ同等の施設を整備することを想定した。 必要なアウトプットは、次のとおりプールの利用のみとし、更衣室などの付属設備はプールの利用に必要なもののみを設置すれば良いものとした。施設用地は市有地を事業期間中無償貸付けとする。 ○25メートル8コースの大人用プール(公式競技が可能なものとする。)と幼児用のプール(100㎡)を有する屋内施設とする(プールは共に温水)。 (2) 前提条件 ア 当施設をPFIにより整備する場合の条件
イ 経済上の条件
(3) リスクの配分 リスク配分は図表Ⅷ―1のとおりである。 図表Ⅷ―1 リスク配分表 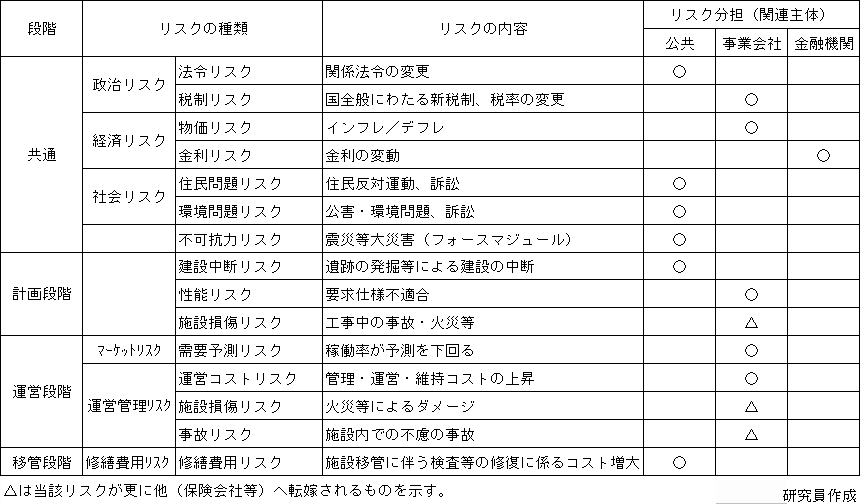
市からSPCへの主なリスクの移転の主なものは次のとおりである。
上記は、運営そのものに直接影響を与えるリスクである。その他に損害賠償のリスク等潜在的なリスクは、市直営でも同様な保険はかけており、公共側が負っても民間側が負っても負担額はさほど変化しないと思われるため、ここでは考慮しない。 (4) PFIとPSCの関係 公共部門が自ら実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値を「PSC」といい、PFI事業として実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値を「PFI事業のLCC」という。PFI事業のLCCがPSCを下回ればVFMが生じる。しかし、SPCが事業を行う場合、経常利益があがることもさることながら、LLCRやEIRRの数値が採算ベースに乗らないと企業が応札しない可能性がある。 (5) PSCの計算 PFI事業とした場合のVFMを算定するために、PSCの計算を行った。 PSCは次に掲げる費用の合計の現在価値である。 (地方債償還費用を含む。ここでは国庫補助金を除く。) ○施設運営費用(運営費から使用料を差し引いたもの。) ○リスク調整(ここでは事故等による損害賠償) 図表Ⅷ-2 PSC算定表
費用については、実際に稼働している類似施設の整備費及び運営費を元にしている。また、公共側が負っているリスクも定量化した。人身事故等に対する損害賠償リスクについては、事故による損害賠償の期待値を得るためのデータが不十分であったため、次のような想定を行って定量化した。
よって、30,000(千円)×2(人)÷10,000(千人)=6(円/人)となった。 建設遅延及び建設費リスクについては、建設期間及び建設費が少ないため、ここでは除いた。しかし今後、リスク調整のための方法等が蓄積されることにより、すべてのリスクが定量化され、VFMを定量として受け止めることができるようになることを期待する。 その結果、PSCは1,352,077千円となった。 (6) PFI事業分析 図表Ⅷ―3 事業スキーム図 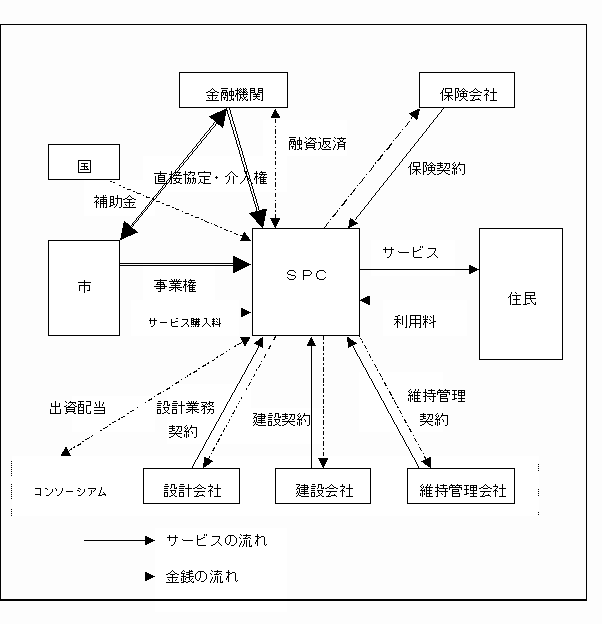
ア 事業スキーム SPCは建設費及び運営費を利用料及び市支払金により回収する。建設に当たっては国庫補助を受ける。出資者には利益を配当する。市と金融機関の間に直接協定を締結し、金融機関の直接介入権を認め、事業破綻を未然に防ぐこととする。 イ キャッシュフロー分析 PFI事業のLCCのキャッシュフローを分析した。(図表Ⅷ-4) その際に次の想定を行った。
この結果、LLCR=1.51、EIRR=8.4、VFM=30,418千円となった。 上記の数値は基本ケースだが、利用者の減少など経済環境の変化はプロジェクトの経済性に影響を与える。キャッシュフローに係る主要なリスクの値を変化させても事業が成り立つかを調べるのが感応度分析である。 事業開始後の主要なリスクとして、利用者数と光熱水費についてキャッシュフロー分析表の数値を入れ替えることで分析を試みた。 ●利用者の減少による場合 利用者が予定の95%、90%、85%の場合を想定した。
●光熱水費の高騰 光熱水費が予定を10%、20%、30%、40%上回った場合を想定した。
(7) 考察 ア PFI事業に係る仕様について キャッシュフロー分析で算定したLLCR及びEIRRの数値を得るためには、SPCは建設及び運営の費用を公共が行った場合の85%に抑える必要がある。これは、建設と運営を一体としたライフサイクルコストを考慮した設計や、性能発注への対応、デザインビルドによるコストダウンによって可能になることを期待している。逆にいえば、これらが満たされないような仕様で発注者(市)側が民間側の創意の余地を奪ってしまえば、このケースではPFI事業として成り立たない。 イ 公の施設の運営と第三セクター 「PFI基本方針」を受けて出された「地方公共団体におけるPFI事業について」(平成12年3月29日付け自治事務次官通知)により、地方自治法第244条の2第3項、第4項、第5項に規定する公の施設の管理受託者等の制限は、PFI事業においても同様であるとされている。これにより、民間出資100%のSPCであっても、維持管理に係る事実上の業務(維持補修等のメンテナンス、警備、清掃など)を包括的に行うことは可能であるが、施設利用料を当該SPCの収入とすることが出来ないため、SPCは全額市からの委託料により資金回収するほかない。また、運営についてはほとんど何の関与もできないため、民間事業者の創意を活かした運営を行うことは不可能である。 しかし、ここではPSCとPFI事業のLCCの比較を試みることを目的にしており、単純化するためにSPCをあえて第三セクターとしていない。 ウ PFI事業完了後の施設の無償譲渡について 事業完了後は、施設をSPCから市に無償譲渡することとなっている。本来であれば、これを有償譲渡とし、施設の状態によっては減額されることを契約に盛り込むことにより、事業期間中に施設保全のインセンティブが働くようにするのが一般的である。しかし、キャッシュフローが複雑になるので、ここでは残存価値が残らないこととして無償譲渡にした。もし有償譲渡ならば、施設の残存価値の算定方法をあらかじめ定めておくことが必要となる。 エ VFMの算定について PSCの算定において「公共部門」としては市のみを想定した。本来的な意味で「公共部門」の支払額を求めるのであれば、国、県が支払う額(国庫補助金等)も考慮すべきであろう。したがってこの事例の場合、PFI事業によって得られるVFMは市にとってのものであって、公共部門全体(国、県、市)のものではない。 また、ここでは、PFI事業においても従来と同じ条件で国庫補助を受けられることとしているが、もし、PFI事業による場合には国庫補助を受けられないケースでは、公共部門に国を含めるかどうかは、VFMに大きく影響する。PFI事業では国庫補助を受けられないような場合、国まで含めて考えれば、補助金支出がなくなることにより公共部門全体としてはVFMが得られるとしても、市単独レベルでは補助金による財政的援助がなくなることに伴う自己負担増により、VFMがマイナスになることもあり得る。この場合市がその事業をPFIで実施しすることは現実的ではない。 オ VFMとアドバイザー等費用 PFI事業の契約手続は煩雑であり、また、専門知識を要することから、従来型に比して手続に係る費用(アドバイザー等費用)が多くかかる。英国の場合、アドバイザー費用は1契約当たり少なくとも約4千万円とされている。これによれば、PFIで事業を行う場合、従来型より少なくとも4千万円は安く実施できなければコストに見合ったVFMが得られたとはいえない。 3 ケーススタディを振り返って 「PFIを研究するならケーススタディをしてみたい。」研究員の中から必然的に湧きあがった意見だった。とはいったものの、どうやったらいいのか皆目見当がつかない。ともかく研究書を読みあさる、手探りの試みから始まった。 まず壁に突き当たったのが、PSCの算定だった。研究員が架空のケースを想定してPSCを算定することは難しかったので、過去10年以内に事業を開始した既存施設の実績値を参考にした。「過去10年以内の施設」としたのは次の理由による。①物価がさほど変わらないので、金額面で比較しやすい。②既に運営が始まっているものは、実際の運営・管理費のデータが得られやすい。(事業期間の公的財政負担の計算ができる)③事業開始当時の実情が調べやすい、などである。 いざ方針は決まったものの予想に反し、開示された情報はなかなか集められなかった。リスクを定量化するデータの収集に至っては困難をきわめた。そのため、全国で発生した損害賠償のデータをもとに仮定した。 研究員は3グループに分かれ、プール事業、保育園事業、公営住宅事業についてのケース検討を行った。本書で取り上げたプール事業以外のケースで、独立採算型のスキームの組み立てを試みたが、事業採算の合うケースにはならなかった。また、既存施設の実体を洗い出していくうちに、従来型の運営の弱点が目についた。「この事業をPFIでやったら効率性をもっと優先するよ。」「自分が運営するんだったら人件費をもっと抑えるな。」といった、白熱した意見がグループごとに飛び交っていた。キャッシュフロー表は、研究員が参考資料をもとに独自に組み立てた。既存施設の生データでの分析では、建物のバックヤードの省力化、人件費の削減、運営形態の改善などにより、ある程度のVFMを生み出すことができた。PFI事業化の流れも一通りたどることができ、研究員にとってはケーススタディに取り組んだ成果はあっただろう。 PFIがVFMを生み出す最大の要因といわれる、ライフサイクルコストを考慮したデザインビルドや性能発注に踏み込むことができなかったため、費用の縮減については仮説を立てざるをえなかったが、一般的に従来発注より1~2割は安くなるといわれていることを踏まえ、事例内容の組み直しを行った。 読者の方には、「公の施設」の法制面の問題をはじめ、不備な点が随所にあるのは承知の上で、PSC、キャッシュフローなどの知識獲得の一助として本書をお読みいただけたら幸いです。
おわりに 報告書はいかがでしたか。 昨年の6月から始まった研究会も、報告書の完成をもって終了のときを迎えました。 PFIは財政支出が削減でき、住民サービスも向上し、そのうえ民間企業に新たなビジネスチャンスをもたらす。そんなキャッチフレーズが気にかかり、自分の自治体でも取り入れたいと思っていた矢先、グッドタイミングでPFIの政策研究の募集があり、すぐに飛びつきました。ところが、一端ひもとくや否や、聞きなれない横文字や専門用語の多さに、経済用語辞典や電子辞書を手離せない自分を不甲斐なく思ったものでした。 最初の数か月は毎回宿題が多く、2週間ごとの研究会の朝、土呂の駅で顔を合わせるとみな疲れきった様子。土日はひたすら、PFI本の読書タイムと宿題の原稿書きになることがしばしば。それでも終わらず、徹夜で勉強して研究会に参加したことも。居酒屋では資料片手に何時間も議論する姿に、お店の人からは白い目で見られる始末。研究会当日に至っては、研究員の間で意見が折り合わず、口論になるのが日常茶飯事。真夏の人材開発センターの食堂で、冷房が効かない中、夜遅くまでヘロヘロになりながら議論したこともありました。 尽きない議論にNever give upのタフな仲間たち。終わりの見えない万里の長城をたどっているような気分でした。しかし、日常業務とは違う分野の勉強が、脳の活性化・老化防止(?)に役立ったことも確かです。長い時間を費やし、考え続けた私たちが到達した「PFI」は、住民の求める公共事業へと変革を起こし、自治体職員の意識改革も推進する力になって欲しいと期待しています。 成果主義の観点からいえば、まず、研究報告書の出来が評価されなければなりません。ですが、ここに至った過程を私たちは大きな収穫だと思っています。他の自治体に、腹を割って話せる「仲間」を見出せたことも今後の人生の貴重な財産になるでしょう。
巻末資料 へ はじめにと目次 に戻る |