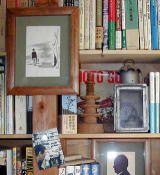
古い本棚
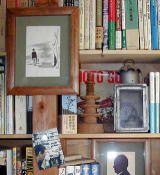
| 「便利な世の中になったものだな。」笑いながら、ミラノの夜のうす暗い街並みを背景に、大聖堂の前で両手を広げてポーズをとる2番目の姉にカメラのレンズを向けながら思った。 普段より少し朝早く起きて、近くの高速インターチェンジのバス停から直行便で空港に向かい、途中1ヶ所の給油着陸はあったものの、その日のうちに、こんな夜の散歩ができるのがウソのようだ。 新書版の薄っぺらな本を選び、書店の書棚から引き抜いたのは何気ない行為だったが、自分にとってはずっと後まで、肺の奥深く呼吸するような感覚を残すことなど、その時は思いもしなかった。 松本には3年の寮生活と、下宿住まいの3年を合わせて6年を過ごし。休日や、仕事の帰り道に、ときどき日米書院に通うようになっていた。店の右奥の書棚の前に佇むことが多く、ギッシリ詰まった本の背表紙を眺めているだけでよかった。 ’70年代松本市は駅近辺も開発の手が大きく入れられる前夜のようで、情緒も残され、今に比べれば多少の不便さはともかく眼には明るい温かさやうるおいを宿す人も多く、裕福な毎日ではなかったが、贅沢な時間を謳歌していたと思う。 サン カルロ広場を探し、教会の右脇のサン カルロ書店の扉を見つけ、確認するように少し周囲を見てまわって、気持ちだけが充満する身体を店の内に運んだ。 限られた時間だが、私たちの他に誰もいない書店の中で、肺の一番奥深くまで、空気が届くような質で満たされ。そこに自分がいることの必然のようなものを感じた。 冊子のような地方の出版物と、わずかな文房具をレジのカウンターにのせ、女主人の顔を見ると、どうして自分がそこにいるのか全部解かっているかのような眼差しが向けられていた。 思わず、「ATSUKO.」と声に出して話題にするより、女主人は私が選んだ地方訛りの言葉づかいで書かれた薄い冊子を1つ1つ、ていねいな言葉で、ちょっと自分の故郷をなつかしむように、説明してくれた。 松本の日米書院は2002年夏に元の伊勢町に移転、新装開店後ほどなく店を閉じる。「ミラノ霧の風景」のあと、数多の須賀敦子さんの著作を取り寄せてもらっていたが、私の宝物のように思っていた本棚は消えてしまった。 須賀さんが大切な時間を過ごされた、コルシア ディ セルヴィもサン カルロと名をかえて、静かな時間の流れの中にある。いつかまた、ミラノを訪ねることがあったら、小さなヘッドホーンで、ムスタキか、レナード コーエンを聴きながら行ってみようかな。古い本棚の前に立って、眼を閉じればあの頃にタイムスリップできるかもしれない。 |
 |
 |