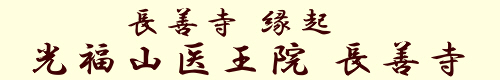| 当山は寄居町鉢形に築城されていた武蔵国鉢形城主北条氏邦(藤田氏邦)の三男「光福丸」の菩提寺として知られ、和歌山県高野山の「金剛峰寺」を本山とする高野山真言宗の寺院です。 鉢形城は天正18年(1590年)豊臣秀吉の関東攻めの際、小田原城主北条氏直(第5代当主)の父氏政(第4代当主)の弟氏邦が城主であったが、前田利家らの大軍の猛攻を受けて降伏開城。氏邦は利家に従い加賀金沢に赴き優遇されていたが慶長2年(1597年)57歳で病没した。 氏邦には四人の男子がいたが長男東国丸は幼逝、二男亀丸は仏門に入り、三男光福丸当時4才が氏邦の命にて養育係町田土佐守秀房に小前田で守られ、慶長2年秀吉より15歳になったら十万石与えるの御朱印を賜るがその後、慶長4年(1599年)7月15日13才で病没。 四男は庄三郎(生没年不詳)で後に氏邦の家督を相続している。 光福丸:天正15年〜慶長4年(1587年−1599年)法名:医王院殿寿林光福大童子 光福丸菩提の為、長善寺が創建されたのは翌慶長5年(1600年)であったが、年代不詳なるが後に火災で焼失した。 寛保3年(1743年)4月法印廣寿代に現在の本堂が完成し、安永7年(1778年)5月法印白明代に総欅造りの 鐘楼門しょうろうもん が建立された。 鐘楼門はその構造のめずらしさから、明治31年8月6日から8月10日に文豪幸田露伴が秩父を4泊5日旅した「秩父紀行」(知々夫紀行)に出てくるが、昭和41年9月25日台風26号強風で倒壊し惜しくも失われ、現在は本堂正面の跡地に金剛力士像が建立されています。 長善寺のご本尊は金剛界大日如来さまであり ご真言は オン バザラダト バン とお唱えします。 ご詠歌は よろずよの ねがいをここに まんがんし ほとけのちかい たのもしきかな とお唱えします。 |
 五三の桐紋 真言宗 宗紋 |
 国道140号境内入り口 |
 三つ巴紋 高野山真言宗 宗紋 |
|
|
 |
|
|
|
|
後北条氏の家督相続 |
|
|
長善寺の創建 慶長5年(1600年)北条氏邦家臣町田土佐守秀房は子の九郎左衛門長延と共に、故光福丸と土佐守の父である康忠入道長善菩提の為現在の地に山号を光福山医王院とする長善寺 光福山医王院長善寺 を創建した。 新編武蔵風土記稿(文化・文政期 1810年起稿し1830年に完成した武蔵国の地誌) 榛澤郡(はんざわぐん)之五 鉢形領之二 小前田村 長谷寺 新田にあり、真義真言宗 江戸本所弥勒寺末、光福山医王院 と記載されています。この 長谷寺 と記載される寺院は同地において他の文献などにその名称見られず、長谷寺の存在した証無く、長善寺がかつて 長谷寺 と呼称された証は発見されず後の明治8年(1875年)6月太政官示達により武蔵国郡村誌が編纂され、時経過して埼玉県から昭和28年武蔵国郡村誌全15巻が刊行され武蔵国郡村誌第十巻、武蔵国榛沢郡巻之五 112Page 小前田村 長善寺 真義真言宗 東京本所弥勒寺の末派なり村の東方にあり ・ ・ ・ 中に小前田村の戸数が記載されており、総戸数百八十八戸その中に寺一戸とあるので、当時小前田村にあったのは長善寺の一寺であった。 学校として公立小学校一所本村長善寺を仮用す生徒数男四十六人女八人 の記載あり。 新編武蔵風土記稿 長谷寺 は寺院名称一字誤りにて記載されたと考えられ、後の武蔵国郡村誌では 長善寺 と記載されています。 新編武蔵風土記稿には小前田村と小前田新田村の二村名の記載あり、武蔵国郡村誌では小前田村 長善寺 村の東方にあり・・・と記載されています。 新編武蔵風土記稿の中に榛沢郡の地図二枚があり、正保年中改定図には小前田村、元禄年中改定図には小前田村と小前田村新田が描かれ、小前田村の東に小前田村新田と描かれています。正保年代(1644〜1648)、元禄年代(1688〜1704)での小前田村”新田”の扱いの違い、いつから使われ、いつ頃に使われなくなり、小前田村だけになったのか? 小前田新田村 だったのか? 小前田村新田 であったのか? 新編武蔵風土記稿には鉢形繁栄の頃迄は小前田新田村は芝地であり、慶長年中に開発され後に小前田村より栄え民の多くが新田に住したと記載されている。 現在の長善寺の住所は埼玉県深谷市小前田ですが、それ以前 (1879年3月17日〜1889年3月31日まで) 榛沢郡小前田村 ※1 (1889年4月 1日〜1896年3月28日まで) 榛沢郡花園村小前田 ※2 (1896年3月29日〜1983年5月31日まで) 大里郡花園村小前田 ※3 (1983年6月 1日〜2005年12月31日まで) 大里郡花園町小前田 (2006年 1月1日) 花園町、岡部町、川本町が深谷市と合併して現在の 深谷市小前田 ※1 国の郡区町村編制法の施行により 1879年3月17日 埼玉県の行政区画として榛沢郡発足 (榛沢郡の名称はそれ以前から用いられている) ※2 小前田村 武蔵野村 永田村 北根村 黒田村 荒川村 六ヶ村合併による花園村の名称は現在の寄居町にあった花園城から ※3 榛沢郡は 1896年3月29日 男衾郡、幡羅郡と共に大里郡に編入され、榛沢郡は当日消滅しています。 新編武蔵風土記稿 榛沢郡の元禄年中改定図に小前田村、小前田村新田の記載がありますが、地名のみで寺院は描かれていません。 新編とは”古風土記”に対して新しいと云う意味で付けられた名称で、他に1842年に完成した新編相模国風土記稿もある。 長善寺縁起におきまして、上の記載内容と過去印刷物内容が異なる部分がありますが、上の内容を史実情報としております。 |
|
|
|
|